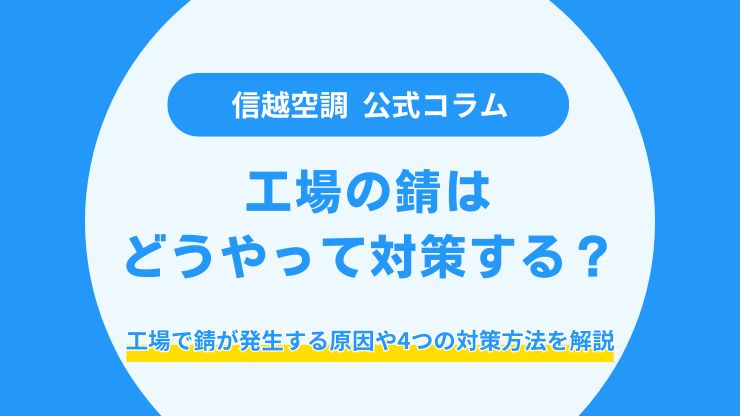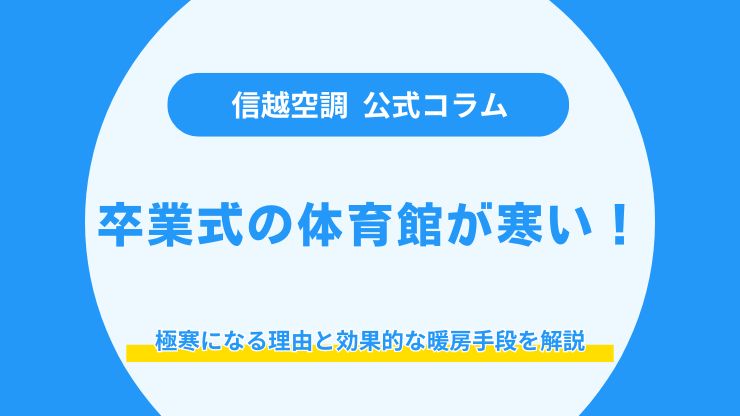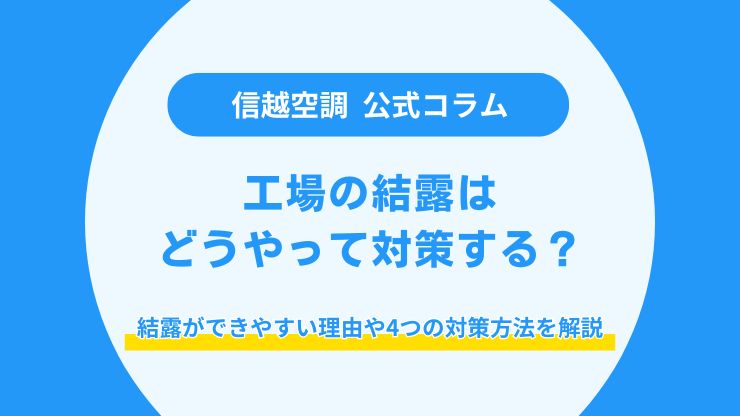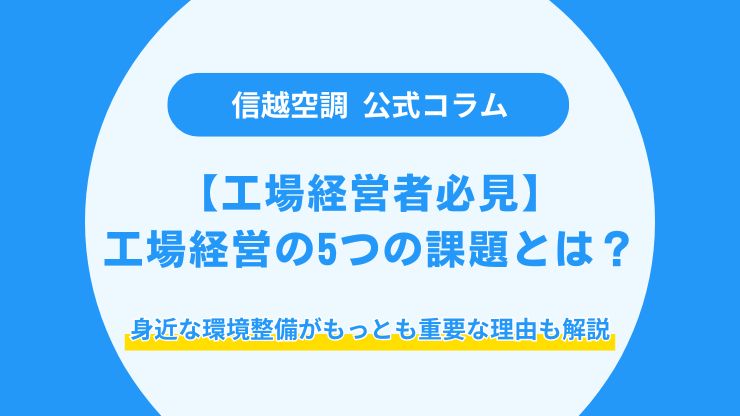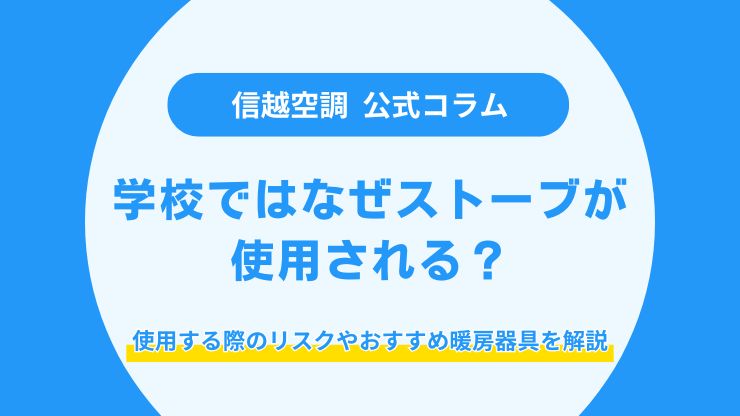保育園の暑さ対策は必須!熱中症の発生シーンや具体的な対策方法を解説
春になると暖かくなり、保育園や幼稚園での子どもたちの活動も活発になってきます。しかし、春から夏にかけて十分に注意しなければいけないのが熱中症です。
近年は猛暑日もかなり増加し、真夏には40度を超える日も増えてきました。子どもたちは体温の調節機能が十分に発達していないので、暑さや熱中症にはとくに気を配る必要があります。家庭から子ども達を預かる保育園・幼稚園は十分に注意しなければいけないのはもちろん、自治体全体で考えなければいけない問題の1つといえるでしょう。
本記事では、保育園や幼稚園の暑さ対策が必須な理由や熱中症が発生しやすいシーン、おすすめの暑さ対策方法について解説します。
1.保育園や幼稚園の暑さ対策は必須
熱中症とは、高温多湿な環境で体温の調節機能がうまく働かず、体内に熱がこもった状態です。保育園や幼稚園に通う乳幼児たちは、特に熱中症のリスクが高いと言われており、十分な暑さ対策が必須となります。ここからは保育園や幼稚園の暑さ対策が必須の理由について解説します。
1.1 子どもは体温調節機能が未発達
乳幼児の子どもはまだ体温調節機能が未発達で、体内で水分や必要な成分を蓄積しておくことが難しいです。汗を出す役割をする汗腺の発達も未発達なので、汗をかきにくく体内に熱がこもってしまいます。その結果、体温が上昇し続けて熱中症につながってしまうのです。
熱中症になると、めまいや立ちくらみ、頭痛、吐き気、だるさなどの症状が現れ、重症になると意識がもうろうとしてしまうので注意が必要です。
1.2 地面の反射熱を受けやすい
子どもは身長が低いため地面との距離が近く、地面の照り返しによる反射熱の影響を受けやすいです。そのため、常に大人より気温が高い環境で過ごしていることになります。
外気温の計測は通常地上150cmを基準としています。たとえば最高気温が32℃の日でも、身長100cmの子どもにとっては35℃くらいに感じているでしょう。
保育園や幼稚園などでは、外での遊びや行事も多くあります。大人が感じている暑さ以上に、子どもたちは暑さを強く感じているということを認識しておきましょう。
1.3 子ども自身で予防できない
乳幼児の子どもたちにとっては、水分補給や衣服の調節など、自ら熱中症予防をおこなうのは難しいことです。また、遊びに夢中になるあまり身体の変化に気付きにくかったり、喉の渇きに気づきにくかったりして、気づいたら熱中症になっていたというケースも少なくありません。
保育園側・幼稚園側で、こまめな水分補給の時間を事前に決めておいたり、子どもだけで行動させないための仕組みを作っておいたりなどの工夫をおこなうようにしましょう。
2.保育園や幼稚園で熱中症が発生しやすいシーン
保育園や幼稚園で熱中症が発生しやすいシーンとして、以下のような場面が挙げられます。
◼︎熱中症が発生しやすい場面
登園した直後
外遊びの直後
プールなどの水遊び後
教室内での遊びの時間
お昼寝の直後
登園した直後や外遊び・教室内の遊びのタイミングなどは注意することが多いと思いますが、実はお昼寝の時間も注意が必要です。睡眠はたくさんの汗をかいて水分が失われるので、お昼寝後は十分な水分補給が重要となります。
また、子どもたちは言葉で自分の症状を説明することが難しいので、大人たちが気にかけてあげることがとても重要です。
3.保育園や幼稚園で暑さを対策するには?
暑い夏であっても、保育園はいつも通り保育がおこなわれます。しかし、子どもたちは大人に比べて熱中症のリスクが高くなるため、大人たちは子どもの異変にすぐに気が付くように行動することが重要です。それと同時に、熱中症にならないように子どもたちができる予防をきちんとしていくことが重要です。
ここからは保育園や幼稚園で暑さを対策するポイントを解説します。
涼しい環境づくり
こまめな水分補給
つば付きの帽子や風通しのよい服を着用させる
暑さ指数(WBGT)の確認
それぞれ詳しく解説します。
3.1 涼しい環境づくり
涼しい環境づくりをおこなうことは、暑さ対策のなかでも重要な要素の一つです。
保育園や幼稚園では十分な空調設備が整っていないこともあるため、涼しい環境を作るための工夫がとても大切となります。屋内でも熱中症のリスクはあります。室内の温度や湿度を計測し、十分な換気や空調をおこなって快適な環境を維持するようにしましょう。
3.2 こまめな水分補給
こまめに水分補給することも、熱中症対策の基本です。遊び時間やお昼寝の前後、プール時間の後などにこまめに水分補給をおこなわせましょう。
子どもたちは喉の渇きや体温が上がっているのを気にせずに活動し続けます。その活動がずっと続くことで熱中症を引き起こしてしまうので、1〜2時間おきに水分補給をするルールを設定するとよいでしょう。一度に大量に水分補給をおこなうのではなく、こまめに適量の水分補給をおこない、身体から水分が失われるのを防ぐことが大切です。
3.3 つば付きの帽子や風通しのよい服を着用させる
屋外での遊び時間や活動時は、つば付きの帽子や風通しのよい服を着用させるようにしましょう。
首元までカバーされたつば付きの帽子は熱中症予防に効果を発揮します。頭や首元を直射日光から守ると、体温の上昇が抑えられ、熱中症のリスクを軽減できます。
また、子どもたちは身体に熱をこもらせてしまう傾向にあるので、風通しのよい服を着用させるのも効果的です。吸収性や通気性のよい麻や綿の素材の服を着用させるようにしましょう。
3.4 暑さ指数(WBGT)の確認
保育園や幼稚園でのその日の予定は、暑さ指数(WBGT)をチェックして柔軟に対応するようにしましょう。
暑さ指数(WBGT)は、 湿度、日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、気温の3つを取り入れた指標です。国際的に規格化されていますので、保育の現場でも活かしていくことで、熱中症の予防をおこなうことができます。
◼︎日常生活に関する指針
暑さ指数(WBGT) |
注意すべき生活活動の目安 |
注意事項 |
|---|---|---|
危険(31以上) |
すべての生活活動でおこる危険性 |
高齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。 |
厳重警戒(28以上31未満) |
外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。 |
|
警戒(25以上28未満) |
中等度以上の生活活動でおこる危険性 |
運動や激しい作業をする際は定期的に充分に休息を取り入れる。 |
注意(25未満) |
強い生活活動でおこる危険性 |
一般に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。 |
※参照:熱中症予防情報サイト|環境省
暑さ指数は環境省の熱中症予防情報サイトでチェックできるので、参考にしながら保育園や幼稚園でのその日の活動を判断するのがおすすめです。
4.保育園や幼稚園の快適な環境づくりは「ヒエスポ」がおすすめ
「保育園や幼稚園に簡単に導入できる移動式エアコンが欲しい」
「効率よく涼しくできる空調設備を取り入れたい」
そうお考えのあなたは、信越空調の「ヒエスポ」がおすすめです。ヒエスポは、広い空間でも活用できる性能の高さから多くのお客様に活用されています。深刻な暑さへの対策や急な空調設備の故障などに対応できることから、最近では自治体や教育機関でも取り入れられていることが増えてきました。
ヒエスポは直進性のある大風量の風が遠くまで届くようになっており、特に冷やしたいエリアの近くに置くことで効果的に冷房ができます。一番小さいサイズで2.8kW、一番大きいサイズで14.0kwの冷房能力を備えており、学校の形状や環境にあわせて幅広い冷房能力から選ぶことが可能です。
また、冷房を使いながら空間を除湿可能なため、乾いた冷気を浴びながら汗を乾燥させることで体感温度をグッと下げることができます。温度が同じでも湿度によって体感温度は変化し、湿度が10%高いと体感温度は1℃高くなるといわれています。湿度を下げることは熱中症の予防にも最適です。
お客様に合わせたさまざまな機種を、販売からレンタル・リースまで幅広く対応しています。ぜひ、信越空調の「ヒエスポ」をご検討ください。
5.まとめ
本記事では、保育園や幼稚園の暑さ対策が必須な理由や熱中症が発生しやすいシーン、おすすめの暑さ対策方法について解説しました。保育園や幼稚園の子どもたちは体温の調節機能が十分に発達していないので、暑さや熱中症にはとくに気を配る必要があります。
各所でも猛暑によるさまざまな問題が発生しているため、責任者や自治体は適切な処置をおこなわなければいけません。熱中症のような事故を起こさないためにも、保育園や幼稚園の暑さ対策は万全にしておきましょう。
もし「冷房機器も効果的なものを導入したい」とお考えの方は、ぜひ一度信越空調にご相談ください。