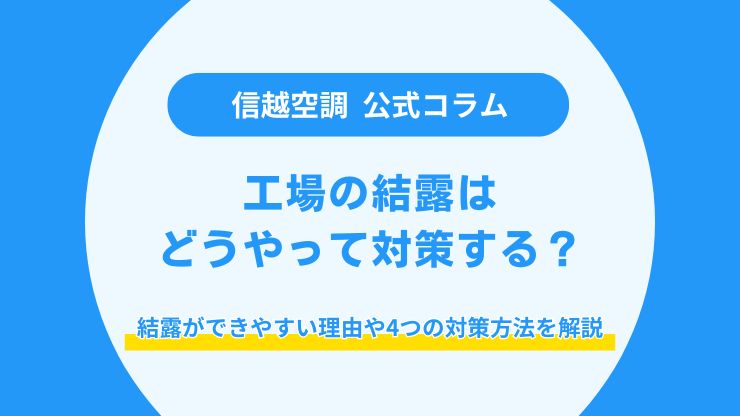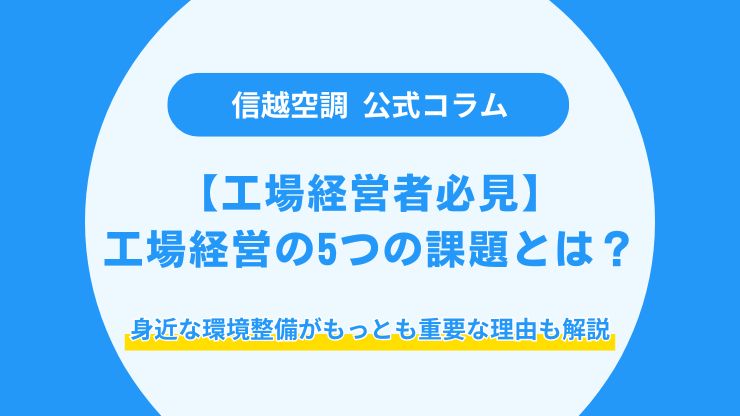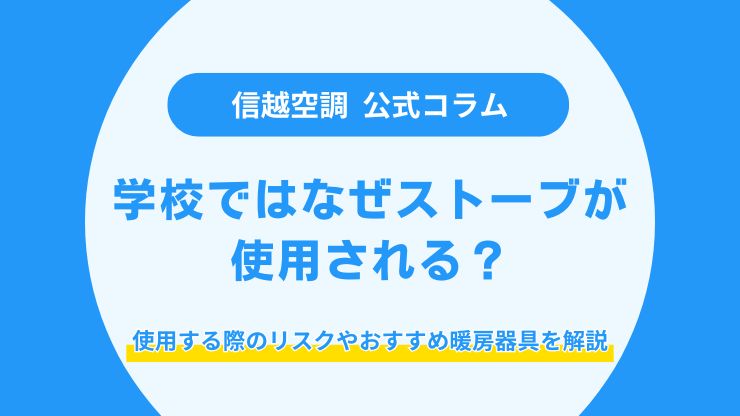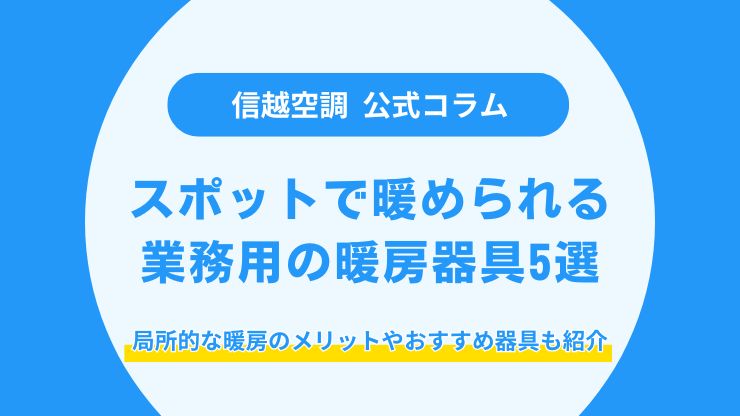工場の冷房が効かない原因と対策|冷房効率を大幅に向上させる5つの方法
夏場、エアコンをフル稼働しても工場内がなかなか冷えず、従業員の作業効率や安全性に不安を感じることはありませんか?
広大な空間、高い天井、金属製屋根への輻射熱、大型設備からの排熱など、工場ならではの要因が複雑に重なり合い、冷房効果を著しく減退させています。
本記事では、まず「なぜ工場は冷房が効かないのか」を分析し、その上で実践的な対策を5つご紹介。最新のスポット冷房機器や運用ノウハウも交え、冷房効率を大幅に改善するヒントをお届けします。
1. 工場はなぜ冷房が効かないのか?
工場や倉庫は面積が広く天井高もあるため、エアコンをフル稼働しても思うように冷えないケースが多いです。
金属屋根の輻射熱や大型機械の排熱、頻繁な扉開閉による外気流入が重なり、冷気が逃げやすいのが理由です。
また、冷房コストが膨らむ一方で、熱中症リスクや生産効率の低下を招く恐れがあります。
本記事ではそんな「冷房が効かない」問題の背景を探り、有効な対策をわかりやすく解説します。
工場や倉庫で冷房が効かない主な原因は、以下の点にあります。
1.1 広大な空間と高い天井構造
工場は数百㎡~数千㎡の広さ、天井高は5~10mを超えることもあります。
冷たい空気は下に沈むので、床面近くはある程度ひんやりしても、上層部はまったく冷えずにムラが生じます。
一般的に人が感じる寒暖差は1mの高さで約0.5~1℃変わるため、高天井では上部に溜まった熱が拡散せず、
全体を冷やすには膨大な冷房能力が必要です。
1.2 屋根からの輻射熱(ふくしゃねつ)
金属折板、瓦棒葺き、スレートなど工場の屋根は夏場に表面温度60℃以上に達すると言われます。
この輻射熱がそのまま屋内に降り注ぎ、天井部分を異常に高温にします。
天井に近い部分が熱源化すると、エアコンで作った冷気が瞬時に打ち消され、設定温度を下げても体感温度は改善しません。
1.3 換気不足と冷気逃げ問題
衛生管理や防音を理由に窓や通気口を最小限にする工場も多く、熱気がこもりやすい密閉構造です。
また、フォークリフト等の出入口が頻繁に開閉されると、せっかく冷やした空気が屋外へ逃げ、
外の熱気が室内に流入します。結果、エアコンは“いたちごっこ”で余計に稼働し続け、効率は大幅悪化します。
1.4 熱を発する機器を多く使っている
製造ラインのモーターやヒートポンプ方式の冷凍機、焼却炉や溶接機など、
多量の排熱を放つ機器が稼働する現場では、常に追加の熱負荷がかかり続けます。
これらの排熱が工場内の空調負荷を押し上げ、エアコンのみの冷房では対処しきれません。
2. 冷房効率を大幅に向上させる5つの方法
上記の要因をひとつずつ解消していくことで、冷房効率を劇的に改善できます。
2.1 定期的なメンテナンス&フィルター清掃
まず最初に取り組むべきは、エアコン本体の基本性能を維持するメンテナンスです。
室内機のフィルターには、時間が経つほどホコリや油分が付着し、吸い込める空気量が徐々に減少します。
実際、フィルターが目詰まりした状態では、定格能力の30~50%も冷風量が低下してしまうことがデータで明らかになっています。
したがって夏季のピーク時には月に一度、フィルターを外して掃除機で埃を吸い取り、水洗いしてしっかり乾かすことを習慣化しましょう。春先と秋口のシーズン変わりにも同様の手入れを行えば、年間を通して冷房能力を損ねずに運転できます。
同時に、室外機まわりの熱交換器(フィン)にも目を配りましょう。周囲の落ち葉や工場排煙に含まれる油分がフィンに付着すると放熱機能が大きく低下し、いわば室外機が“サウナ”状態になってしまいます。これを防ぐには、定期的にエアダスターやブラシでフィン表面の埃を吹き飛ばし、年に一度は専門業者による高圧洗浄を依頼すると安心です。
こうしたメンテナンスを怠らないことで、室内外の熱交換がスムーズになり、エアコンの運転効率がクリアに戻ります。
2.2 室外機周辺の環境改善
室外機は屋外に設置されるがゆえに、直射日光を浴びたり、周囲の熱風を再吸込みしたりしやすい場所です。
この環境を少し手を加えて改善するだけで、室外機全体の温度を10~15℃程度下げることが可能になります。
たとえば、簡易なすだれやシェードを立てかけるだけで直射日光を遮ぎり、
室外機を覆うパラソルを取り付ける方法もあります。
これによりフィンの表面温度がぐっと下がり、放熱効率が格段にアップします。
また、周囲の地面に打ち水をするという昔ながらの手法も侮れません。
地面に撒いた水が蒸発する過程で気化熱を奪うため、室外機まわりの局所的な気温を5~10℃ほど低下させる効果があります。
ただし、室外機本体には直接水をかけないよう注意し、あくまで周辺地面に水を撒くことがポイントです。
さらに、フィン前方約50cm、側面も1m以上は障害物を排除することで、
吐き出した熱気を再吸込みする「ショートサーキット」を防止し、フル回転時のパフォーマンス低下を抑えられます。
2.3 断熱・遮熱対策の強化
次に、建物本来の断熱・遮熱性能を引き上げる対策が求められます。
まず壁や天井に断熱材を追加施工すると、外気の熱侵入を防ぎつつ、内部冷気の流出も抑えられます。
グラスウールやロックウール、あるいは硬質ウレタンフォームのような素材を適所に敷き詰めることで、
年間冷暖房負荷が20~30%削減できるケースもあります。
屋根面には近赤外線を反射する遮熱塗料を塗布する方法が効果的です。
一般の塗料では吸収されてしまう波長帯の太陽光を50~80%反射する機能を持ち、
施工後すぐに屋根表面温度が10~15℃下がります。耐用年数は製品によって異なりますが、
5~10年程度で塗り替えを行うことで長期的な効果維持が可能です。
さらに工事期間を短縮したい場合には、屋根上に設置できる遮熱シートや断熱パネルを活用しましょう。
これらは塗装工事に比べて準備から施工までがスピーディで、大面積にも対応できる点が魅力です。
いずれの方法も、屋根裏や天井の輻射熱を本質的に抑えることで、室内の冷房負荷を大きく軽減します。
2.4 局所での冷却ソリューションの導入
工場全体を一律に冷やすよりも、人や機械が集まる“熱スポット”をピンポイントで冷やした方が
はるかに効率的な場合があります。
そのために活躍するのが、配管工事不要でキャスター移動が可能なスポットクーラーや移動式エアコンです。
電源コンセントさえあれば設置から稼働までが即日完了し、
特に暑さが厳しいラインや検査エリアに近づけることができます。
たとえば組み立てラインに沿って数台の移動式エアコンを配置し、
作業者が最も熱を感じやすい位置に向けて冷風を集中させることで、
全体冷房負荷を50%以上削減した実例もあります。
また、小ロット生産の出荷検査場では、スポット冷却機器を使うことで品質チェック時の集中力を高め、
製品不良率を低減するといった効果が得られます。
局所冷却を併用することで、メインの業務用エアコンを無理にフル稼働させる必要がなくなり、
ランニングコストの大幅削減につながります。
2.5 空気循環の最適化
最後の一手として、工場内の空気循環を見直します。
大型サーキュレーターや天井取り付け型ファンを設置し、
冷気が下層に溜まるのを防いで上層へ押し上げることで、天井付近の温熱層をかき混ぜ、温度ムラを解消できます。
この取り組みだけで、エアコンの設定温度を1~2℃上げても同等の体感涼感を維持できるようになり、
年間の冷房コストを10~20%削減できるデータもあります。
また排熱ポイントに局所排気ファンや給気フードを新設し、ライン排熱を効率的に屋外へ排出することで、
熱気が室内にこもるのを防止します。こうして室内の冷気と外気が絶妙に循環する環境をつくることで、
エアコンのパフォーマンスを引き出し、工場全体の冷房効率を飛躍的に向上させることができるのです。
以上の5つの対策を組み合わせて実施すれば、工場内の冷房効率は格段に向上し、
従業員の働きやすさはもちろん、企業の光熱費削減や生産性向上へと直結します。
まずは小さな取り組みから始め、効果を実感しながらステップを進めてみてください。
3. 5つの対策を“ワンストップ”で実現するポイント
工事不要で即日使える移動式エアコンをお探しなら、信越空調の「ヒエスポ」が最適解です。
「ヒエスポ」は本体に室内機・室外機を内蔵し、コンセント接続だけで稼働可能。
断熱補強や遮熱塗装などの建物側対策と併用することで、冷房効率を劇的に高められます。
直進性の高い大風量で狙ったエリアにピンポイント冷風を送り、全体冷房負荷を大幅に削減。
加えて除湿機能も備えているため、体感温度をしっかり下げて熱中症リスクを抑えながら、
省エネ運転を実現します。
購入・レンタル・リースのいずれにも対応し、予算や運用期間に合わせた導入が可能です。
ワンストップで進める冷房効率改善の仕上げとして、ぜひ「ヒエスポ」をご検討ください。
5.まとめ
本記事では、工場の冷房効率を低下させる原因と、その具体的な改善策を5つご紹介しました。
エアコンの定期メンテナンスとフィルター清掃で本来の性能を引き出し、
室外機まわりの日よけや打ち水で熱負荷を抑制。断熱材・遮熱塗料による屋根・壁の熱侵入防止、
サーキュレーターによる冷気循環の最適化、そして移動式エアコン「ヒエスポ」を活用した局所冷却で、
全体の冷房負荷を大幅に削減できます。
これらを組み合わせることで、従業員の快適性と生産性を両立しながら光熱費も抑制可能です。
導入のご相談は信越空調までお気軽にお問い合わせください。