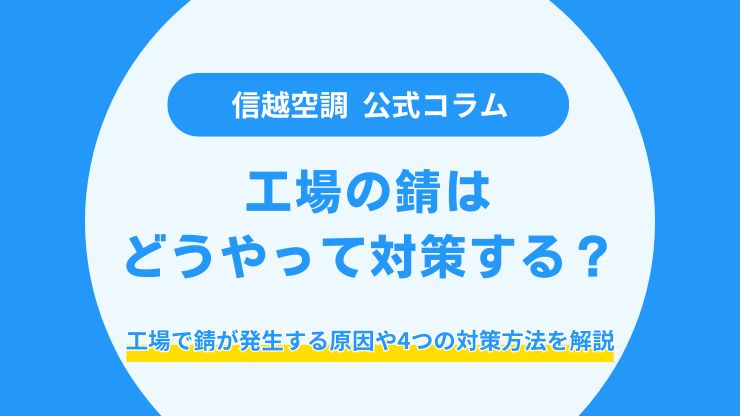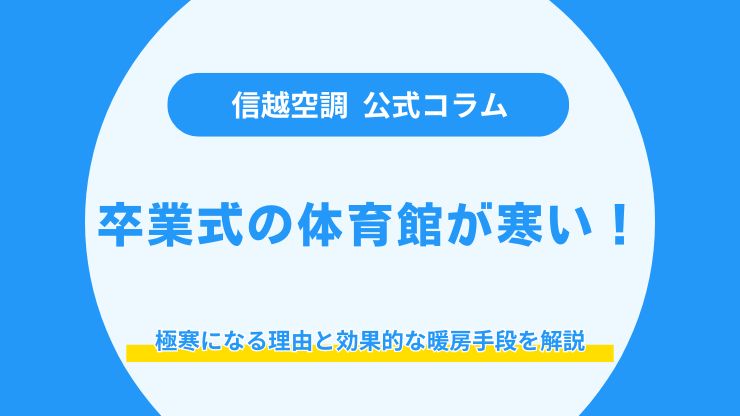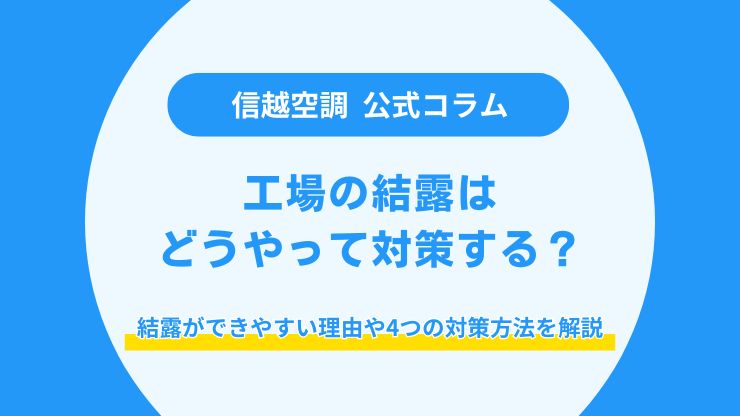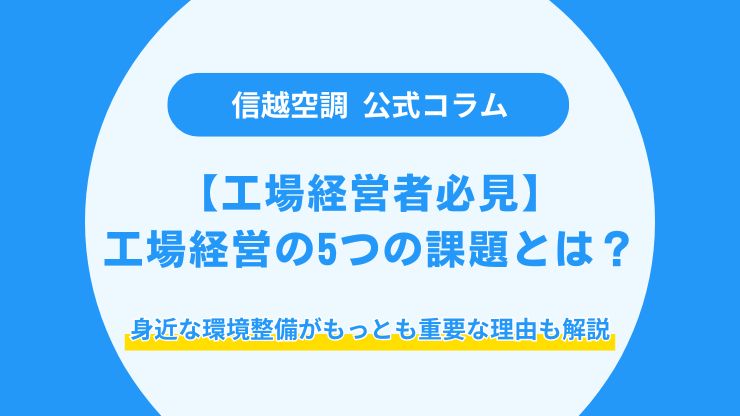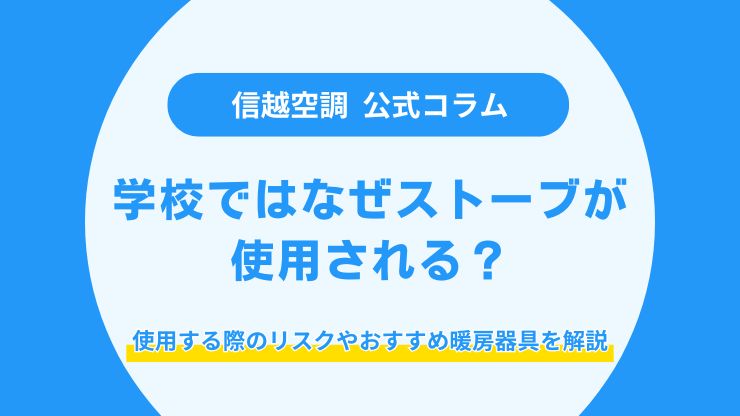学校の暑さ対策は必須!児童生徒の安全と学習環境を守る方法を徹底解説
全国的な猛暑が続く近年、学校現場では35℃を超える普通教室、40℃に達する体育館が珍しくなくなりました。
「授業が終わるころには教室がサウナ状態」「体育館が40℃近くに達してクラブ活動が中止に」
といった悲鳴が全国から上がっています。
熱中症リスクの高まりだけでなく、集中力の低下・ICT機器の故障・教職員の健康被害など影響は多岐にわたります。
本記事では、学校が取り組むべき効果的な暑さ対策を解説します。
1. なぜ学校は暑さ対策をおこなうべきなのか?
全国的な猛暑が続く近年、学校現場では35℃を超える普通教室、40℃に達する体育館が珍しくなくなりました。
「授業が終わるころには教室がサウナ状態」「体育館が40℃近くに達してクラブ活動が中止に」
といった悲鳴が全国から上がっています。
熱中症リスクの高まりだけでなく、集中力の低下・ICT機器の故障・教職員の健康被害など影響は多岐にわたります。
本記事では、学校が取り組むべき効果的な暑さ対策を解説します。
1.1 熱中症から児童生徒・教職員を守るため
子どもの身体は大人より水分量が多く体表面積も大きいため、外気温の影響を受けやすく、
短時間でも体温が上昇しやすい特徴があります。
身長が低いぶん照り返しの輻射熱をまともに浴び、熱中症リスクが高まります。
文部科学省の統計では、学校管理下での熱中症搬送例の68%を小中学生が占めています。
組織的な暑熱リスク管理は、もはや「努力義務」ではなく教育機関の必須業務といえるでしょう。
1.2 学習効率と集中力を維持するため
米コロンビア大学の研究では、室温が30℃を超えると読解・計算の正答率が8〜14%低下することが報告されています。
気温がわずか2℃違うだけでもテスト結果や授業理解度に影響するというデータもあり、
冷却不足は授業の質そのものに直結します。
高温環境では脳への血流量が減少し、認知機能や短期記憶、論理的思考力が低下するため、
思考力・判断力・表現力を重視する新学習指導要領の実践には、集中できる環境が必須なのです。
1.3 部活動・体育の安全を確保するため
屋外競技だけでなく、体育館や武道場でも輻射熱で室温が急上昇します。
暑さ指数(WBGT)28を超えると激しい運動は原則中止が推奨されており、冷却設備と運用基準の整備が不可欠です。
「大会が近いから」「練習時間が確保できないから」という理由で危険な状況でも活動が継続されることがあります。
クラブ顧問が「まだ大丈夫」と判断する前に、数値で制限ラインを共有する仕組みが必要です。
1.4 ICT機器・教材を守るため
タブレット端末は内部温度が45℃前後で自動的に性能を制限し、
プロジェクターや大型モニターも高温で寿命が短くなります。
夏場の冷房不足はICT機器の動作不良や故障リスクを高め、機器故障と追加予算という形で跳ね返り、
デジタル授業計画を停滞させかねません。また、紙の教材や図書も高温多湿環境では劣化が早まります。
2. 学習効果を高める教室の適温は?
文科省「学校環境衛生基準」は教室の室温を17〜28℃、相対湿度を30〜70%に定めています。
実際には25〜26℃・湿度45〜55%が集中力と快適性のピークという調査が多く、
先進的な自治体の指針もこの温湿度ゾーンに設定されています。
温度と湿度のバランスを適切に保つことで、児童生徒の集中力維持時間が20〜30%延長するという研究結果もあります。
2.1 全館空調だけでは校舎全体を快適に保ちづらい理由
老朽校舎は断熱性能が低く、単独空調では冷気が逃げやすい構造になっています。
教室・特別教室・体育館・廊下と空間特性が異なるエリアを一括制御すると、最も暑い部屋に合わせて出力を上げるしかなく、
電力コストが2〜3倍に跳ね上がります。しかも温度ムラは解消できません。
体育館などの大空間では天井高が高いため、冷気が下方に行き渡りにくく、
地上付近の実効温度が設定温度より大幅に高くなりがちです。
したがって建物の熱負荷を下げ、ピンポイント冷却を組み合わせる「多層防御」が鍵になります。
全館空調を基盤としつつ、追加的な対策を組み合わせることで、より効率的かつ効果的な温熱環境管理が可能になるのです。
3. 学校で実践できる暑さ対策 3選
3.1 スポットで涼しくする機器の導入
移動式エアコンや大型送風機を朝礼台付近・配膳室・職員室など温熱リスクの高い場所に設置し、
必要な時間だけ稼働させます。メリットは以下の通りです:
・設置工事が不要で、必要な場所へすぐに移動できる機動性
・通常の100Vコンセントで使用可能で、電源工事が不要
・夏季や特定行事期間だけの限定使用が可能でコスト抑制
・全体空調を28℃設定にしていても、必要な場所のみ体感温度を下げられる
実際の事例では、体育館の全校集会で舞台周辺にスポット冷房を設置し、登壇者の熱中症リスクを大幅に軽減できたケースや、図書室の閲覧エリアに送風機を配置して利用者数が増加した例もあります。
3.2 遮熱カーテンと遮熱塗料の活用
南向き窓に遮熱カーテンを取り付けると日射熱を最大60%カットできます。
遮熱カーテンの特徴は:
・一般カーテンと比較して日射遮蔽効果が2〜3倍高い
・視認性を確保しながら熱だけを遮断する高機能タイプも選択可能
・既存のカーテンレールに取り付け可能で後付けが容易
また、屋根や外壁へ近赤外線反射塗料(遮熱塗料)を塗布すると屋根表面温度が10〜15℃下がり、上階教室の輻射熱を大幅に抑制できます。
メリットには:
・屋根や外壁の劣化防止と長寿命化
・屋上階や最上階の教室の温度上昇を効果的に抑制
・塗装工事は夏休み期間に完了でき、授業への影響を最小化
・耐用年数が7〜10年と長く、中長期的なコストパフォーマンスが高い
実際の事例では、遮熱塗料の塗布により最上階教室の最高温度が5℃以上低下し、熱中症リスクの高い日数が40%減少したという報告があります。
3.3 緑陰づくりとミスト噴霧
ゴーヤやクズウリで「緑のカーテン」を形成すると葉の蒸散作用で周辺気温が2〜3℃低下します。
緑のカーテンの利点:
・設置コストが低く、児童生徒が育成管理に参加できる教育的効果
・二酸化炭素の吸収による環境貢献と環境教育の実践
・収穫物を家庭科や給食に活用できる食育効果
・また、昇降口や渡り廊下にミスト装置を設置して外気自体を冷却すれば、
校舎への熱侵入を抑えられます。微細な水滴の蒸発による気化熱で周囲温度を3〜5℃下げることが可能です。
参考情報:
・文部科学省「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」
・環境省熱中症予防情報サイト「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き(概要版)
4. 移動式エアコンなら《ヒエスポ》がおすすめ
「体育館での全校集会が15分で限界」「文化祭の準備期間だけ強力に冷やしたい」
―そんなニーズに応えるのが信越空調の《ヒエスポ》です。
工事不要:100Vコンセントに差すだけで稼働。老朽電源にも対応。
大風量直進送風:最大20m先まで届くため体育館ステージでも強力冷却。
除湿モード:湿度を効率的に下げ、体感温度を3〜4℃低減。
レンタル・リース対応:夏季や行事のみの短期導入が可能。
移動性の高さ:キャスター付きで女性教職員でも簡単に移動可能。
既存空調・遮熱塗装と組み合わせれば、総電力を約30%削減しながらWBGTを安全域に維持した事例も報告されています。
導入校からは「児童生徒の集中力が向上した」「熱中症の救急搬送が前年比でゼロになった」との評価があります。
5.まとめ
本記事では、学校における暑さ対策の必要性と具体的な方法について解説しました。
児童生徒の健康と学習環境を守ることは、教育機関にとって最優先すべき課題です。
遮熱カーテンや遮熱塗料による建物の熱負荷軽減、緑陰整備による外気温のコントロール、
そして移動式エアコン《ヒエスポ》を活用した局所冷却を組み合わせることで、
猛暑日でも安全で快適な教育環境を実現することが可能です。
学校の暑さ対策は単なる設備導入だけでなく、運用ルールの確立や教職員の意識向上、
児童生徒への熱中症予防教育も含めた総合的な取り組みが重要です。
文部科学省の「学校における熱中症対策ガイドライン」や環境省の熱中症予防情報サイトも参考にしながら、
各学校の実情に合わせた対策を講じていくことが望まれます。
もし「より効果的な冷房機器を導入したい」「体育館や行事の冷却対策に悩んでいる」
といった課題をお持ちであれば、ぜひ一度、学校施設への導入実績も豊富な信越空調にご相談ください。
専門スタッフが各学校の状況に合わせた最適なソリューションをご提案いたします。